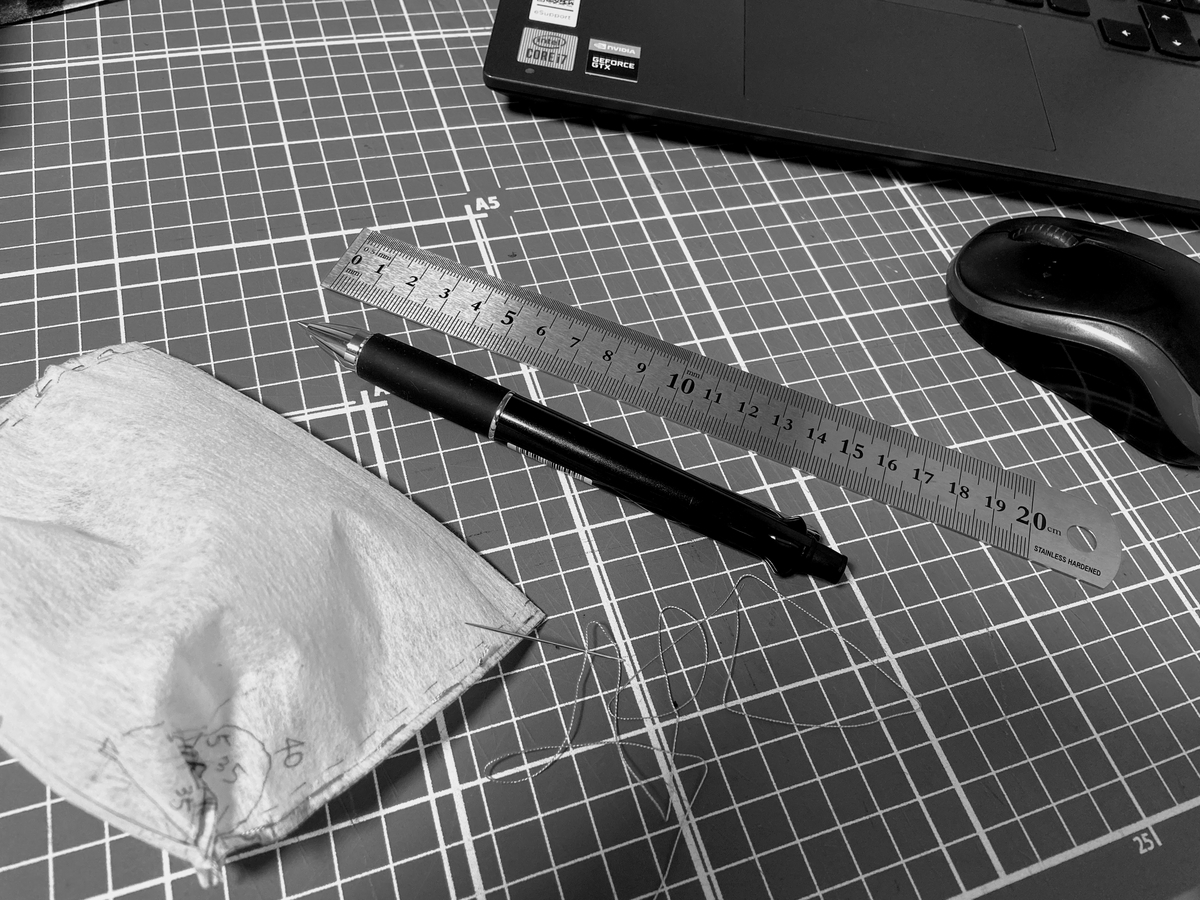
型紙を描けるソフト
自分は、PCに向かって、CADでレザークラフトの型紙を作るときがあります。
以前は最初から最後まで、手書きで型紙を作っていましたが、CADやIllustratorのようなソフトで型紙を描くほうが、曲線がキレイに描けたり、サイズが正確に印刷できたりして、おすすめです。
もともとイラストを描くためのソフト、Illustratorでも、型紙の線を描くことが可能です。Illustratorは、基本的には有料ソフトです。お試し期間のみ、無料で使用できます。
一方、主に建築・機械系の図面などを作成するためのCADソフトには、自分が知っているだけでも無料で使えるものが2つあります。無料ソフトとはいえ、かなり高度な作業まで可能で、使用者も多く、サポートのコミュニティサイトなどもあります。
レザークラフトの型紙を描くだけであれば、いずれのソフトでも、基本の幾つかの操作を覚えれば描けてしまいます。今まで使ったことがない、という場合でも、正確な型紙を残しておくことができますので、チャレンジしてみても良いかと思います。
アナログか、デジタルか
自分の場合は、最初からPCでソフトを起動して作るのは、ほぼ平面で考えれば作れるような、2Dのものだけです。
立体的な3Dの作品の型紙は、頭の中でなかなか寸法が出せません。難しいですね。
型紙の製作でやっかいなのは、一箇所のサイズを変えると、連動して、別の所もサイズが変わることがある、という点です。
理由は、単に、縦、横、高さ、といったサイズの変更時だけでなく、使用する革の厚みが関係するためです。
このように、立体にしなければならないものは、PCの前で考えて型紙を描いても、必ず仕上がった時に誤差が生じます。
そのため、自分の場合は、はじめはアナログな手作業(鉛筆で手書き)で型紙をおこし、作品を作ってみて、何度も修正し、「これで良し!」という段階になったら、最後にCADで型紙を描いてデジタル化して保存しておく、という手順で行っています。
革の厚みの影響
先ほど書いた「革の厚みの影響」についてです。
実際に考えたパーツを組み立てててみて、その後に型紙に修正が生じてくる理由は、殆どの場合、革の厚みの影響ではないかと思います。
昔、レザークラフトを始めたばかりの頃、一つの種類の型紙に対して、どんな厚みの革でも作れるのだろうと思っていました。
というより、レザークラフトの型紙というものは、革の厚みが考慮されて作られているものだ、という意識が無かったのです。
レザークラフトの本に載っている作り方の型紙などには、たいてい「胴に使用する革は1.5mm厚のタンニンなめし革」とか、「内側のポケットに使用する革は1.0mm厚のタンニンなめし革」とか、書いてあると思います。
それなのに、注意書きを完全に無視して作ったところ、革が厚すぎて縫えない、とか、革が薄すぎて金具を留めるのに弱すぎた、とか、色々な障害が生じて、うまく作れなかったことがよくありました。
革という素材は、布よりも、使う厚みのラインナップが大きい素材です。
革を薄くして使う場合は0.3mm厚位から、厚い革を使う場合は2mm厚以上、と、同じ型紙で同じ作品を作るにしても、革の厚みが違うと、全く別物に仕上ります。
0.5mm位違うと、「形は同じだけれど、別の物」になります。
そのため、革の厚みは、型紙を描く際にも、必然的に関係してくる要素です。
型紙を描く際は革の厚みを考慮する、これがとても大事な点です。
模型
そういうわけで、最近は、とりあえず、はじめに「模型」のような物を作っています。
大きな鞄の場合などは、実際の半分位のサイズで作って、CADに描く際に、数字を倍にしても良いですが、なるべく実際のサイズで作ったほうが、そのまま型紙のサイズが決まるので、便利かと思います。
いきなり頭の中だけで考えて型紙を描く作業は、誰でも難しいのではないでしょうか。そのため、一度、模型を作ってみる、というのは、メリットが幾つかあります。
まずは、やはり、イメージを掴めることです。
例えば鞄だったら、幅、高さ、マチのバランスとか。
「内布のファスナーポケットの幅はこれ位が良いかな?」とか。
「こんな上からポケットを付けたら手が入れにくいかな?」とか。
「ここに金具を付けようと思ったけどスペースが足らないかも?」とか。
「芯材はどのあたりに貼れば良いかな?」とか。
このような感じで、イメージを掴みやすくする、それがメリットです。
そして、レザークラフトに欠かせない、革漉き部分の把握がしやすいことです。
革漉きは、箇所によって、段漉き、斜め漉き、と漉き方に加えて、漉く厚みも違いますので、それを箇所ごとに考えて、メモしていきます。
模型を見ながらパーツの組み合わせを考える
「どこで革を裁断して、どこでパーツを繋げようか?」その点も、模型があったほうが、考えやすい点です。
どんな素材でどんな物を作る場合でも、パーツが1パーツだけのほうが、2つ以上のパーツを接着する手間がかからず、間違いも起きず、作業工程が簡単です。
しかし、それには、革の大きさが必要で、不要箇所を切り落とす場合は無駄も出てしまいます。
例えば、ミシンで縫うような大量生産品の作りを見ると、できるだけコストを抑えるため、1つのパーツで無理して作ることよりも、革を無駄にしないで裁断する、そちらを優先していることが多いと思います。
ミシンで縫うのは一瞬ですから、無駄な革の廃棄量が増えて原価が上がるより、良いのでしょうね。
それに対して、ハンドメイドで自分だけの作品を作る場合は、そこまで考える必要はないので、好きな形で、型紙をおこせば良いと思います。
ただし、そもそも、1種類の厚みの革だけではきれいな作品が作れない場合もあります。財布など、複数のパーツで構成されている作品は、何種類も異なる厚みの革を使うことが多いです。
全てを同じ厚みの革で作ると、形の収まりが良くない、デザイン的に不格好、使い勝手が悪い、など、色々な問題が生じることがあります。
同時に、作業手順を考える
さらに、型紙を完成させるには、作業工程(パーツの組み立て手順)をどうするか、を考えなければなりませんが、そのときも、模型はとても役に立ってくれます。
「縫いかたを外縫いにするか、内縫いにするか?」
「パイピング、捨てマチなど、サブパーツを組み合わせた縫いかたにするのか?」
「内側に内布を付けるのか?」
「ポケットは外側にも内側にも付けるのか?」
上記の項目は、一つ変えると全体のデザインが変わってしまう項目です。
そして、多くの場合、項目を一つ変えると、縫い代の関係で型紙のサイズを大きくしなければならなくなったり、パイピングを付けるための巻革が必要になったり、内布を付ける際の当て革を追加したり、色々と変更が生じます。
模型を見ながら、縫い代の幅を何mmにしようか?考えたりします。
また、模型は、各パーツの作業手順で、
「ここは先に縫っておかないといけないなー」とか、
「ここはファスナーを先に付けたほうが、手間がかからないかな?」とか、
そういった細部の作業手順を考えるのにも役立ちます。
模型を作る素材
模型を作ることは、試作品を作る前の段階でイメージを持つことができて、大変に便利なのですが、今回のブログ記事の写真にあるような、不織布のような薄い素材で作ると、決定的なデメリットが発生します。
そう、革の厚みを再現できていない点です。
そこで、模型作りには、使う予定の革とほぼ同じ厚みの芯材を使うと、再現性が増すと思います。
芯材によく使われる、バイリーンやスライサーは、もともと様々な厚みのバリエーションで販売されていて、模型への使い分けにもおすすめです。
型紙を作る前に、まず模型を作る、
レザークラフト、本当に面倒です(笑)

leatherworksthalia.hatenablog.com